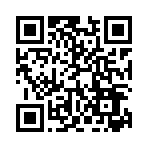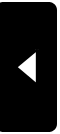2010年09月13日
稲刈り セルフビルド
昨日は、山里暮らし交房”風結い”で
稲刈りとセルフブルドのワークショップでした。
前のたんぼでは稲刈

子供達も

刈り取った稲は藁で束ねます。

昔ながらの”はさ掛け”地元の方にお世話になりました。

子供はいずこへ。
いつの間にか大人だけになっていました・・・。

こちらは、セルビルド。
講師の福井さんに手ほどきを受ける参加者の方
後ろには、プロの大工さんも!

機械を使う人

全部手で作業する人、いろいろです。

稲刈り、セルフビルドの参加者の皆さんと一緒にお昼ごはん


皆さん、お疲れさまでした。
2010年09月10日
いちじく
今日は清々しい秋晴れでした。
暑がりの私も、午前中はエアコンを使わずに過ごせました。

事務所の前の畑にイチジクの木があります。
毎年実がたくさんなるのですが、誰も収獲せず、鳥のエサになっていました。

今年も実がなり始めたので、こっそり収獲します。
朝収獲したら、夕方にはもう違う実が熟していました。
調べてみたら、1日で熟すから、”いちじく”といういのだそう。
2010年09月08日
白露 天然ヤマ 根曲がり フローリング
今日は、白露。
”秋の気配が深まり、露の量も多くなる”というが、どうなんでしょう?
台風で、秋の気配を少し感じましたが、まだしばらくは暑い日が続くのでしょうか?
事務所の前の田んぼは、台風の前に刈り取りが終わったようです。

先日、Aさんの大黒柱の伐採のあと、現場近くの”天然ヤマ”に行ってきました。
栗本さんが林業を営んでおられる朽木地域の山では、昔から天然杉を利用するために、広葉樹の本数を減らして、天然杉の成長を促進させる独特の林業が行われてきました。そのような森を、この地域では「天然ヤマ」と呼んでおられます。

「天然ヤマ」の様子
天然杉というのは、落ちた種が芽吹いたものや、木の根元から芽吹いた枝が、雪の重みで地面に着き根が張ったものが、そのまま大きくなったもの。写真に写っている細いもので50年くら(お兄ちゃん)、太いものは150年くらい(おじいちゃん)は経っているそう。写真にはあまり写っていませんが、足元には太さが数センチで腰くらいの高さの杉が、光が当たるのをじっと待っています。それでも20年くらい(子供)は経っているそうです。そんな天然杉の間に広葉樹がポツポツ育っています。
そんな天然杉の森も、成長した量をこえないよう大切に伐って利用すれば、健全な森の姿を保つことができます。森の働きを維持することを考えながら、その恵みを享受すること、これが地域の資源を循環させる地産地消の家づくりだと思うのです。

根曲がり杉
長い年月を風雪に耐えきたため、根元がこんな風に曲がっています。力強い!

そんな根曲がり杉を、無駄なく生かした住まい

こちらは、天然杉のフローリング
昨年の冬(H21年1月)、朽木は湿気を含んだ重たい雪に見舞われ、木の先が折れてしまう、雪折れの被害が出ました。本来雪には強い天然杉も、この異常な雪には耐えられなかったよう。栗本さんが、丁寧に伐採をし、搬出されたものを、有効に使わせていただきました。
この天然杉のフローリングは、モデルハウス”もりいえ”で体感していただくことができます。

古い伐り株からは、新しい命が芽生えていました。
杉、檜、ヤマモミジ。さて、どの木が育つのでしょうか?
2010年09月06日
まもなく・・・
今日は、結びめの打ち合わせで”風結い”に来ました。
この週末行う、セルフブルドと稲刈りの相談です。

セルフビルドは、”風結い”(写真の右側)に屋根をつくるというものです。
これまで、基礎石を据え、近くの山から木を伐り出し、皮をめくり、刻みを進めています。
(↑これまでの様子はこちら)
残りの刻みが順調に進めば、12日に上棟です。
セルフビルドと言えば、この小川も自分たちで造りました。
庭師。椿野さんにご指導いただき、楽しかったです。

こちらは、稲刈りをする田んぼです。


電柵をしていますが、猿に入られたようです。
この週末までなんとか被害が広がらないように!
そして、間もなく完成の住まい。

外観をチラリ

ポーチの柱には、樫の古材を使い

リビングには、ケヤキの古材を。栗本さんの太鼓梁もあります。

ダイニングからは、蓬莱山を望むことができます。

2階からは琵琶湖も

新築だけと、集落に馴染んでいます。
2010年09月05日
唐揚げに挑戦
今日は休日

ひそかに唐揚げを作ってみようと思っていたので、挑戦しました。

サラダも作ったのですが、作りすぎて、唐揚げが付け合わせに?

鳥モモ肉に、塩、黒コショウ、一味、ゴマ油で下味を付け、
冷蔵庫で2時間寝かせます。
にんにく、しょうが、リンゴをすったものと、塩、お酒を合せたタレに漬け込み、
さらに4時間冷蔵庫で寝かせます。
これで下ごしらえは完了!!
いよいよ揚げ。片栗粉をまぶし、余分な粉はざるでふるい落としておきます。
こうすることで、余分な油がつかず、いいのです。

温度は180℃。我が家のコンロは大阪ガスのガラストップコンロ!
温度設定ができるので、タイヘン楽チンです。
時々、油から上げ空気に触れさせます。
余分な水分が蒸発し、カラっと揚がるのだそう。

はい、完成!家族にも好評でした。
また、挑戦します